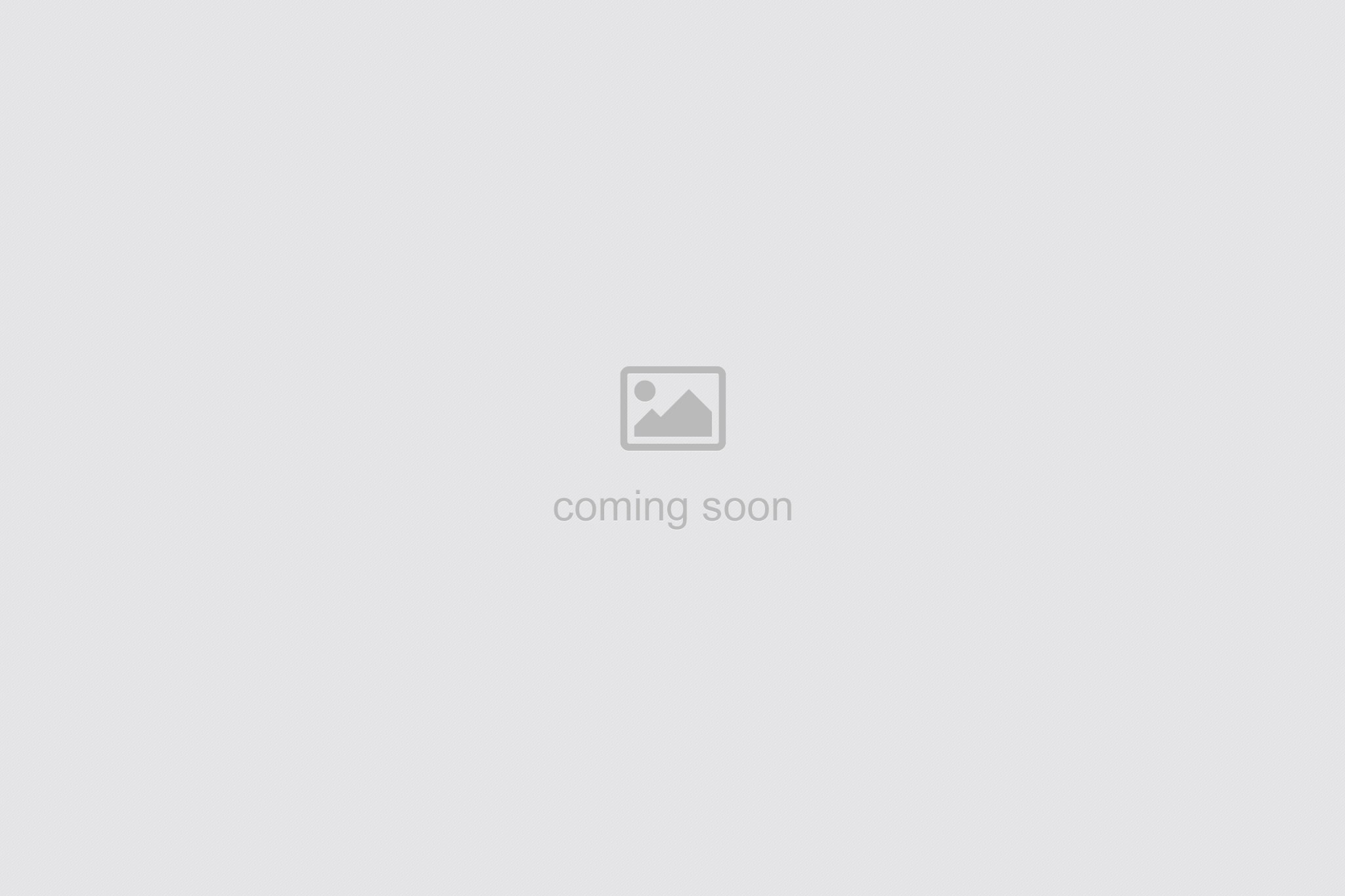法話(オンライン法話のテキスト版です)
令和5年 1月 法話
法話1
南無阿弥陀仏 オンライン法話へようこそお参りくださいました。 民生委員をさせて頂いていた時、赤ちゃん訪問といって、生後2~3ケ月くらいの赤ちゃんのお宅を訪問をさせて頂いておりました。 あるご家庭を訪問した時のことです。 お母さんとお話をしようとしましたが、お母さんに抱っこされた赤ちゃんが泣き止まず、お母さんはただおろおろするばかりでした。 それで、「赤ちゃんを抱っこさせていただいても良いですか?」と、声を掛けると 「はい」と仰るので、赤ちゃんを抱っこさせて頂き、 「蓮くん おりこうさんねー 元気に育ってねー」 と、 声をかけながら、ゆりかごを揺らすようにゆっくり揺らしていると、 赤ちゃんが泣き止んでニッコリ・・・・それを見ていたお母さんが 「泣き止んだ! 笑ってる!」と・・・・お母さんが涙を流しているのが見えました。 赤ちゃんは、再び、お母さんの胸に抱かれて、部屋の方へアンケートを取りに行かれました。 すると、お母さんに抱っこされた赤ちゃんが、さらに大きな声で鳴き続けていました。 玄関に戻ってこられたので、 もう一度、抱っこさせて頂き、 同じように、名前を呼びかけながら、ゆりかごを揺らすように揺らしていると、赤ちゃんは気持ちよさそうに眠ってしまいました・・・・ それを見ていたお母さんは・・・・*「眠ってる!」 と言ってまた涙を流しました。 「赤ちゃんとの生活を楽しんではどうでしょうね」・・・と言ってお宅を後にしました。 お母さんは、赤ちゃんが泣いても、涙を流し・・・赤ちゃんが眠っても涙を流す・・・・両方のお母さんの姿を見せていただきながら、 サトウハチローさん言葉を思い出していました。 ♪ 「弱くて強くて 不思議な母さん 悲しい時には そんなに泣かず 嬉しい時には 涙をこぼす・・・」 やがて、「私がおかあさんよ! ママよ!」 という、親の呼びかけ・親心が赤ちゃんに到り届いて 赤ちゃんは、「おかあちゃん! ママ!」と呼ぶようになることでしょう。 赤ちゃんが呼んでいるようですが、呼ばせているのはお母さん! 同じように、私の口から、 「南無阿弥陀仏」 と出て下さるまでに、阿弥陀さまから どれほどの「お呼びかけ・親心」 をいただいていることでしょう。 一か月程して再び訪問すると、お母さんの懐に抱っこされ、丸々と元気そうな赤ちゃんと、お母さんが玄関に・・・ 「その後どうですか?」 ・・ 「あれ以来、泣きません。 よく眠ってくれて助かります」と、 嬉しそうに、優しく赤ちゃんを見つめる お母さんの姿がありました。
法話2
光源寺オンライン法話へようこそお参り下さいました。どうか気を楽にして少しのお時間お付き合い頂ければと思います。
先日あるお参り先でご門徒の方に「最近、『あなかしこー、あなかしこー』て聞こえるとくると、お経が終わるんだ、ということが分かりました。これはどーゆー意味なんですか?」という質問を受けました。
御命日のお参りのお勤めの最後は「御文章」を拝読させて頂き、その「御文章」は「あなかしこ あなかしこ」で終わります。
「御文章」とは分かりやすく言うと、お手紙のことです。誰のお手紙かと言いますと、第8代宗主、蓮如上人の書かれたお手紙です。
これは特定の個人に宛てて書かれたものではなく、当時の浄土真宗の教えに対する様々な誤解を正すために出され、その数は二百と数十通あるとされています。
乱れる世の中において命の危機に怯える人々に対して、ただ阿弥陀仏におまかせする一念の信心によって、老いた人も若い人も、男性も女性も、そのままの生活のままで救われるという、浄土真宗の教えをわかり易く説き示されております。
そして本題であります「御文章」の「あなかしこ」とは、「もったいないことです」という意味で、仏様のそのおはたらきを感謝するお言葉で締められています。
実はこの「あなかしこ、あなかしこ」の読み方は厳しく定められていて、それはこちらの日常勤行聖典にも細かく記されています。
「あなかしこ あなかしこ」は、本文の最後の音と同じ高さで、二度とも同じように読みます。最後は、特に長く引くようなことはしません。
と、このように記されています。
私が京都でお経の勉強をさせて頂いておる時、当時私はこの「御文書」の拝読が少し苦手でありました。「御文章」の文字は現代の文字とは違い昔の言葉、言い回しである為、その読み慣れない文字を間違えないように読むことに必死でした。
あがり症な私はとにかく前の日に練習を沢山して、その緊張が練習による自信によって程よい位になったところで、当日の指導に臨むわけでございます。
当日、練習通り拝読することができ、ホッと気を抜いて、最後に「あなかしこ、あなかしこ」と読むと、ご講師の先生にそれはもう厳しくご指導を受けました。
「最後のその御文が大切なんです、有り難く頂いて下さい」と、このようにご指導下さったことを今でも覚えております。
今年、浄土真宗のみ教えが開かれて800年をお迎えすることになります。
800年前から今日まで、変わりゆく時代の中で、決して変わることのないこのお念仏のみ教えが、受け継がれてきた法灯が、今私に届いて下さっている。
思い返してみますと私がお念仏の教えに出遇わさせて頂けたのも、小さい頃からあの手この手で私にお念仏を伝えて下さった祖父母、両親、そしてご門徒の方々のお陰様であると改めて感じさせて頂きます。
そのみ教えを、伝えて下さった先人の想いを「あなかしこ、あなかしこ」と、「自分にはもったいないことでこざいました」と頂戴していきたいと、ご門徒様の一つの質問によって考えさせられた、今回のご縁でございました。
先日あるお参り先でご門徒の方に「最近、『あなかしこー、あなかしこー』て聞こえるとくると、お経が終わるんだ、ということが分かりました。これはどーゆー意味なんですか?」という質問を受けました。
御命日のお参りのお勤めの最後は「御文章」を拝読させて頂き、その「御文章」は「あなかしこ あなかしこ」で終わります。
「御文章」とは分かりやすく言うと、お手紙のことです。誰のお手紙かと言いますと、第8代宗主、蓮如上人の書かれたお手紙です。
これは特定の個人に宛てて書かれたものではなく、当時の浄土真宗の教えに対する様々な誤解を正すために出され、その数は二百と数十通あるとされています。
乱れる世の中において命の危機に怯える人々に対して、ただ阿弥陀仏におまかせする一念の信心によって、老いた人も若い人も、男性も女性も、そのままの生活のままで救われるという、浄土真宗の教えをわかり易く説き示されております。
そして本題であります「御文章」の「あなかしこ」とは、「もったいないことです」という意味で、仏様のそのおはたらきを感謝するお言葉で締められています。
実はこの「あなかしこ、あなかしこ」の読み方は厳しく定められていて、それはこちらの日常勤行聖典にも細かく記されています。
「あなかしこ あなかしこ」は、本文の最後の音と同じ高さで、二度とも同じように読みます。最後は、特に長く引くようなことはしません。
と、このように記されています。
私が京都でお経の勉強をさせて頂いておる時、当時私はこの「御文書」の拝読が少し苦手でありました。「御文章」の文字は現代の文字とは違い昔の言葉、言い回しである為、その読み慣れない文字を間違えないように読むことに必死でした。
あがり症な私はとにかく前の日に練習を沢山して、その緊張が練習による自信によって程よい位になったところで、当日の指導に臨むわけでございます。
当日、練習通り拝読することができ、ホッと気を抜いて、最後に「あなかしこ、あなかしこ」と読むと、ご講師の先生にそれはもう厳しくご指導を受けました。
「最後のその御文が大切なんです、有り難く頂いて下さい」と、このようにご指導下さったことを今でも覚えております。
今年、浄土真宗のみ教えが開かれて800年をお迎えすることになります。
800年前から今日まで、変わりゆく時代の中で、決して変わることのないこのお念仏のみ教えが、受け継がれてきた法灯が、今私に届いて下さっている。
思い返してみますと私がお念仏の教えに出遇わさせて頂けたのも、小さい頃からあの手この手で私にお念仏を伝えて下さった祖父母、両親、そしてご門徒の方々のお陰様であると改めて感じさせて頂きます。
そのみ教えを、伝えて下さった先人の想いを「あなかしこ、あなかしこ」と、「自分にはもったいないことでこざいました」と頂戴していきたいと、ご門徒様の一つの質問によって考えさせられた、今回のご縁でございました。